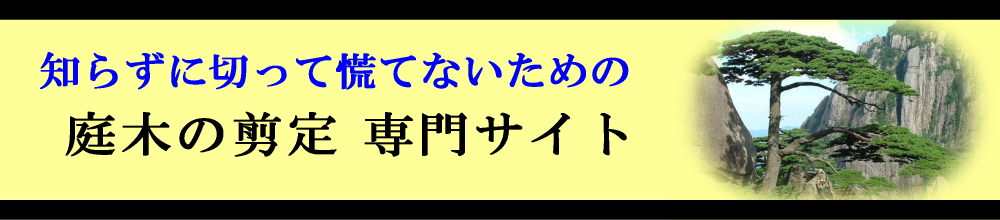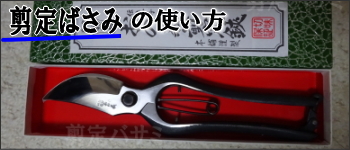樹木の葉っぱにこんなコブのような気持ち悪い突起を見たことがありませんか?

この正体っていったい何だと思います?
子供の頃これに似た葉っぱを見つけたことがあったんですが、気になってその時もやっぱり気持ちが悪かったけど破ってみたんです。
そうしたら
・・・
何もなかった!
大人になって見ても気持ちが悪いです。
虫こぶとはなんだ?
この気持ち悪い正体は「虫こぶ」っていうのですが、虫こぶというのはいろんな寄生生物の寄生によって、植物体が異常な成長をすることで形成されるんですが、その時に植物組織が異常な発達を起こしてできるこぶ状の突起のことなんです。虫えい(ちゅうえい)とも呼ばれています。
寄生(きせい)という言葉をよく聞くと思いますが、この場合の「寄生」の意味ってわかっていますか?
寄生というのは「共生」の一種のようです。「共に生きる」と書きますが全くその通りで「ある生物A」が「他の生物B」から栄養を持続的かつ一方的に収奪する場合の言葉のようです。
虫こぶはよく葉っぱに見られますがその他にも草類の茎や樹木の細枝、花や果実などに見られることもあるようです。昆虫の寄生によって形成されるものが多いようですが、ダニや線虫によるもの、菌類や細菌によるものもあり、すべてをまとめて虫こぶと呼ぶ場合が多いです。

マニアックですが「日本原色虫えい図鑑」という図鑑もあるらしいです。
↓ ↓ ↓
虫こぶのでき方
虫こぶのでき方ですが、例えば栗にできる虫こぶの場合クリタマバチというハチが寄生元で起こります。虫こぶの出来方は、クリタマバチが幼虫をその中で育てるために栗の新芽に産卵して膨れることで虫こぶができます。寄生したら栗の実はなりません。
クリタマバチの成虫は体長3mmくらいの小さなハチで、7月頃成虫になり虫こぶから外に出ます。
1.成虫になったクリタマバチはすぐに新芽に産卵する
→2.孵化した幼虫は芽の中にもぐり込んで越冬する
→3.翌年の4月項から幼虫の入った芽が異常に肥大して虫こぶになる
→4.幼虫は虫えいの内部を食べながら急速に成長して蛹から成虫になる
→1.成虫になったクリタマバチはすぐに新芽に産卵する
クリタマバチはこの4サイクルを繰り返して虫こぶはできます。
はじめに卵の状態のころは虫こぶはそれほど目立たないですが、幼虫、蛹と成長していくうちに大きく膨れ上がり色づいて立派な虫こぶとなるみたいです。
クリタマバチがクリに寄生してできる虫こぶを説明しましたが、他の樹木も虫や菌類による違いはあるかもしれませんが同じように虫こぶが発生するのではないかと思います。
虫こぶは病的なものは恐ろしく感じますが、美しい色のものやどことなくアートさえ感じるものまで存在します。なんでこんな綺麗な虫こぶになったのかはわかりませんが、綺麗なものほど毒があるといいますから見た目では判断できないです。もしかしたら危険なものなのかもしれませんよ。

でも虫たちの生態には感心させられます。例えば先ほど例に挙げたクリタマバチの場合栗の新芽に卵を産み付けるとその住みかが自分のエサになりおまけに外敵もいないわけですから苦労しないで大きくなれるわけです。そんなことをどこから教わるのか、本能に備わっているのかわかりませんが、その生態には感心させられます。
虫こぶの中身は何が入っているの?
虫こぶの中身は、クリの例で言いましたがクリタマバチの幼虫が虫こぶの中で大手を振って生き抜いて成虫になる時期を待っています。ほかの虫たちも同じように生きていることだと思います。細菌類についてはよくわかりません。
虫こぶを切断したら、中にクリタマバチの幼虫が寄生していた!