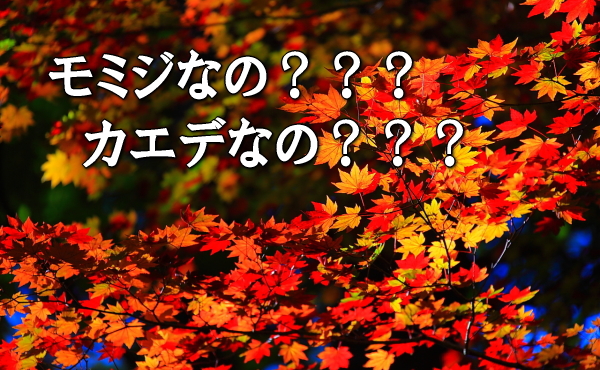
カエデはムクロジ科(旧カエデ科)カエデ属の総称です。
従来のカエデ科は、新しいAPG植物分類体系ではムクロジ科に含められ変わったようです。
ここでは、モミジとカエデの違いって何なのか解説します。
モミジともカエデも、どちらもカエデ属(Acer)の植物ですが、日本では一般的に「モミジ」と「カエデ」と区別されることがあります。
この違いは、主に日本の文化や伝統的な呼び方によるもので、植物学的には明確な区別はありません。
以下で具体的にモミジとカエデの違いの説をわかりやすく説明します。
モミジってなんですか?
夏には旺盛に葉が生い茂るので、手入れに手間がかかり嫌われる気配が漂うモミジです。
しかも、意外と病害虫に弱く枯れやすいです。
そんなモミジも秋には赤や黄色に色づき、モテモテになるというのですから、その代わりようには興味深いものがあります。
モミジの種類には、イロハモミジとかヤマモミジとかが有名で、ホームセンターなんかで苗木が販売されていることもありますよね。
さて、ひとつ質問ですが、
モミジは何科なのかわかりますか?
・・・
私にはわかりません。
・・・
カエデはムクロジ科(旧カエデ科)カエデ属の総称ですが、モミジは何科なのかわかりませんです。
それもそのはず。
「そもそもモミジという種類の木はない!」といことをご存知でしたか?
「えっ、そうなの!」という声が聞こえそうですが、
モミジとカエデの違いは、葉が何枚で・・・とか、大きさの違い・・・だとか、そういう単純なものではないという事です。
「それじゃぁ、いったいモミジはなんなの?」という疑問が浮かび上がるわけです。
さて、「モミジ」を「紅葉」とかくのは知ってますよね!
その紅葉(こうよう)は、主に落葉広葉樹が落葉の前に、葉の色が変わる現象のことを指します。
そこから来ていると思うのですが、本来、紅葉というのは「葉の色が変わり紅葉する木」のことを指すわけです。
だから本来のモミジは、決まった特定の樹種の名前を指すわけでなく、
カエデだろうが、ブナだろうが、ナラだろうが、ガマズミだろうが、ニシキギだろうが、
秋に、葉が落ちる前の落葉広葉樹で、葉が赤色や黄色に変わる現象の木たちは全て、紅葉(モミジ)と呼びます。
なぜ紅葉(こうよう)をモミジと呼ぶのか
では、なぜ「紅葉」を「モミジ」と呼ぶのか気になりますよね。
その昔、元々紅葉は「もみち」と呼ばれていたようです。
秋に草木が赤色や黄色に変わることを「もみつ(紅葉つ)」や「もみづ」といわれ、その連用形で名詞化したのが「もみち」のようです。
平安時代に入ると、「もみち」は「もみぢ」と濁音化され「もみじ」へと変化したといわれます。
それが今では「カエデ」はどこでどう変わってきたのか、ほとんど「モミジ」と同義語のように使われています。
ちなみにカエデの語源は、葉の形がカエルの手に似ていることから、古くは「かえるで(蛙手)」と呼ばれ、「かへんで」や「かへで」となり、「かえで」となったと言われます。
盆栽の世界ではモミジとカエデを区別して使っているようです。
イロハモミジのように葉の切れ込みが5つ以上のカエデ属だけをモミジと呼び、
その他のカエデ属をカエデと呼んでいるみたいです。
それは、聞いた話ですが・・・(^^♪
モミジとカエデの一般的な違い
モミジとカエデには、一般的な考えとしていくつかの違いがあるようです。
1. 葉の形の違い
モミジ(紅葉)は、葉の切れ込みが深いものを指すことが多いです。
たとえば、「イロハモミジ」や「ヤマモミジ」などは、葉が手のひらのように広がり、細かく切れ込んでいます。
例:イロハモミジ(Acer palmatum)
カエデ(楓)は、葉の切れ込みが浅いものを指すことが多いです。
葉の形が丸みを帯びており、切れ込みが少ないものや浅いものをカエデと呼ぶことがあります。
例:オオモミジ(Acer amoenum)
やっぱり、カエデもモミジも同じ属名(Acer ●●●)がつくんだーね。
2. 日本文化における呼び方の違い
モミジは、紅葉(こうよう)する木の総称として使われることも多いです。
特に秋になると赤や黄色に色づく葉を「モミジ」として愛でる文化があります。
例:「紅葉狩り」という言葉は、秋のモミジを見る行為を指します。
カエデは、葉の形状に注目して呼ばれることが多く、樹木として一般的に指される場合が多いです。
要するに、
モミジは、生活するうえで一般的な立場や会話上で多く利用されている表現のようで。
カエデは、学術的な樹木の立場として一般的に指される表現のようです。
3. 紅葉の色づき方
モミジは、赤く鮮やかに色づく品種が多いです。秋の風物詩として親しまれます。
カエデも色づきますが、品種によっては黄色や橙色が主体のものもあります。
4. 言葉の由来
モミジの語源は「揉み出づる」に由来し、秋に葉が赤く染まる様子を指しています。
カエデの語源は、葉の形がカエルの手に似ていることから「蛙手(かえるで)」と呼ばれたことが由来です。
モミジとカエデの違い結論
モミジとカエデは植物学的にはどちらもカエデ属に含まれます。
日本では一般的な考えとして、葉の切れ込みや文化的なイメージによって区別されることが多いとされます。
簡単に言うと、モミジは葉の切れ込みが深く、紅葉が美しい品種を指す傾向が強いとか、
カエデは切れ込みが浅いものを指すことが多いなどという違いがあるといわれます。


